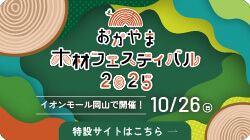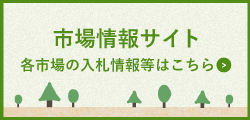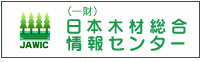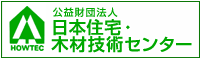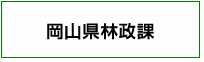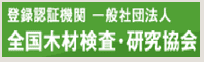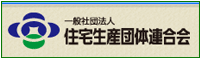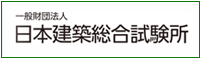耐震性能
- 木造住宅は地震に弱いと聞きましたが、阪神大震災では、倒壊をまぬがれた建物がたくさんあるそうです。その理由と地震に強い建物にするための対策を教えてください。
- 軽くて、強い木材でできている木造住宅は、けっして地震に弱いということはありません。最近の建築基準に基づいて建てられた住宅は、阪神大震災でも大きな被害は受けていません。地震に強い建物にするためには、良質な木材を柱、梁、土台に使用し、筋かいなどを入れた耐力壁を適切に配置した耐震構造にすることです。
地震力は重さに比例
同じ重さの鉄と木の強さを比べると、スギ材でいうと、圧縮の強さは鉄の約2倍、引っ張りの強さは約4倍もあります。地震によって建物が受ける地震力(振動エネルギー)は、建物の重さに比例するので、日本のような地震の多い国では、軽くて、強い木材で家をつくることが適しています。
木造住宅を強くする対策
2. 耐力壁は釣り合いよく配置する。
3. 基礎を一体の鉄筋コンクリート造とし、1階の耐力壁の直下には、必ず基礎を設ける。
4. 土台には、ヒバ、ヒノキ、JISまたはJASの防腐処理木材等を使用する。
5. 柱、梁、土台には太い木材(ひきたて津NPOu12cm以上)を使用する。
建築材料の比重、強度、および比強度
| 材料 | 木材 | コンクリート | 鉄 | |
| 比重 | 0.40 | 2.00 | 7.86 | |
| 引っ張り | 強度 | 900 | 40 | 4,000 |
| 比強度 | 2,250 | 10 | 509 | |
| 圧縮 | 強度 | 380 | 200 | 3,500 |
| 比強度 | 950 | 100 | 445 | |
| 曲げ | 強度 | 700 | 20 | 1,000 |
| 比強度 | 2,800 | 7 | 182 | |
出典:木と日本の住まい[(財)日本住宅・木材技術センター]
建築材料の比重、強度、および比強度
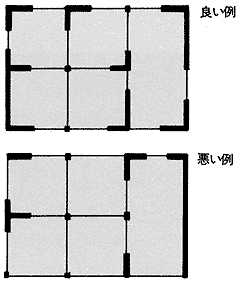
耐力壁が少なかったり、片寄って配置すると、地震に弱くなる。



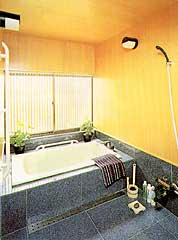
地震に強い住宅にするために
地盤(宅地)
1. やわらかい土が厚く堆積している河川沿いの軟弱地盤に建てる場合は、硬い地盤のときよりも建物を強くつくる。
2. 沖積低地(※1)や低湿地などを埋め立てた砂層地盤では、地盤の液状化現象(※2)が起こりやすいので、一体の鉄筋コンクリートの布基礎にする。
3. 沼、水田、湿地、谷、海岸などを埋め立てた地盤は、揺れやすいだけでなく建物を支える力を失ったり、地割れが生じ、建物が足元から壊れる心配がああるので、とくに基礎を丈夫にする必要がある。
4. 山地や丘陵地など盛土した敷地の建物の基礎は、不同沈下(※3)で壊れるおそれがあるので、擁壁と基礎をしっかりさせる。
軟弱地盤の建物は地震に弱い
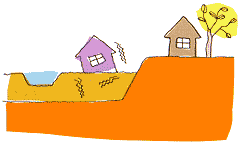
崖、急斜面での建築には注意
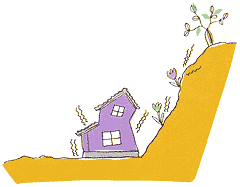
基礎と土台
無筋の基礎は地盤の弱いところでは危険
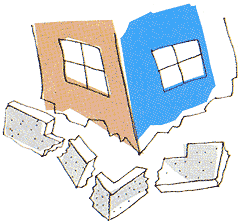
アンカーボルトで土台を布基礎に緊結
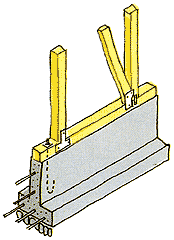
布基礎には鉄筋を入れる
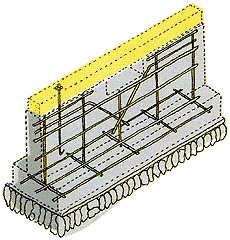
柱の太さ
柱は屋根や2階が支えられる十分な太さにする
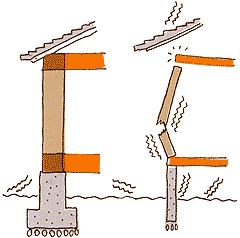
耐力壁の量と配置
1. 耐力壁の総量(総延長)は、法令で最低値が決められている。また、耐力壁は、2階より1階のほうに多く必要になる。
2. 耐力壁は、片寄らないように釣り合いよく配置する。とくに建物の南側は、採光のために大きく開放されがちで、耐力壁が不足し、片寄った配置になりやすいので、注意が必要である。
筋かいを入れたり、構造用合板を張って耐力壁にする
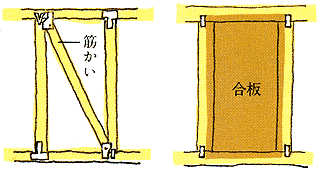
筋かいは向きの異なるものを一対にし、幅は高さの3分の1以上になるようにする
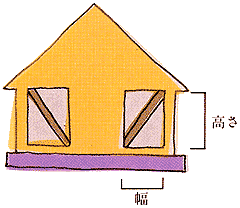
床、屋根
耐力壁画不足したり、片寄った配置になると地震に弱くなる
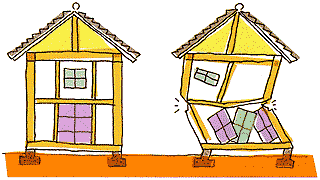
建物の形と重さ
木造住宅の骨組み
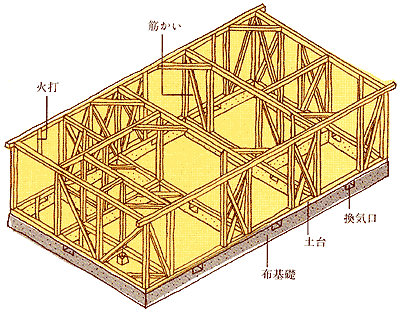
※1 沖積低地とは、約1万年前から現在までに堆積した軟弱でしかも地下水位が地表面に近い地盤のことである。
※2 液状化現象とは、水をいっぱいに含んだ砂地盤が揺さぶられて液体のようになることをいう。
※3 不同沈下とは、建物の基礎が凹凸に沈下することをいう。宅地の造成で盛土の厚さが一定でなく、まだよく締まっていない状態で建築したときに起こる。建物は宅地造成後少なくても1~2年たってから建築するのがよい。
※4 布基礎とは、柱列、壁下に沿って細長く連続した基礎をいう。
※5 耐力壁とは、地震や風に抵抗する壁体で、(1)筋かいの入った壁、(2)構造用合板や石膏ボードなどを張った壁、(3)木ずり壁、土塗り壁、などがある。